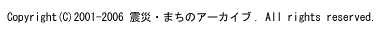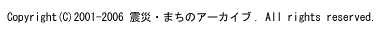一方の端にふれたら、他の端がゆらいだ。
これは、チェーホフの短編「学生」(訳・松下裕)のなかに出て来る。新約聖書の終章、裏切りのペテロに関するものだ。風などなかったのに、なぜゆらいだのか。
端というのは面白い場所である。木の先端ならそこで開花が始まり、鵙の早贄の場所でもある。橋の先端は他界であり、橋の下の淀みには身元不明の死体が浮かんでいる。道の先端はどこまでも未知であるが、足自身に歩みを止めることは出来ない。一歩後退、二歩前進などという発想もあるが、歴史の歩行をおもうと、稗史、私は躓きに関心が向かう。端が同時にゆらぐとは、いかなる事態なのか。そういえば、まさに一変した白骨、焼きあがった骨をつつく生者の箸は、物となった死者の何に触れているのだろうか。
春まだ浅い夕暮れ。鶫のさえずりのなか、神学生が歩いている。次第に濃くなる夕闇の散歩という、この時間の設定がいい。寒さがぶりかえし、その日は真冬のようだった。外套を通して肌に食い込む冷気。かじかむ指先、足の先、痛みのため、先端はことごく硬直する。炎がなつかしい。闇のなかの焚火。いっしんに手をかざす人影に学生は近づく。千九百年前のあのひとも道に躓き、おもわずたたずんだに違いない。風が顔を撃つ。【リューリクの時代にも、ヨアン雷帝の時代にも、ピュートルの時代にも、これとそっくりの風が吹いていた】、捕縛される寸前のイエスにも吹き、貧しさや憂愁、【憂愁や、こういう周囲の荒地や、暗やみや、苦しい感じーこうした恐ろしさはみな、昔もあったし、今もあるし、これからもあるだろう。そしてなお千年たっても、】そうおもったとき、学生は家へ戻る気が失せていた。見れば、農作業を終えた農婦がもの思いに沈みながら炎を見つめている。「なんと冬に逆もどりですね」と、青年は焚火に近づきながら言った。そのとき胸によぎるもの、イエスを裏切るペテロの姿だった。「ちょうどこんなふうな寒い晩に、使徒ペテロも火にあたってたんだろうね」、炎の暗い中心をいっしんに見つめながらつぶやく。
嗚咽する農婦をチェーホフは描く。焚火のなかから語られる青年の言葉。彼はペテロの裏切りの情景を語る。するとじっと聞き入っていた老婦が、いきなり泣き出したというのだ。しかも穏やかな微笑を残して、ここがチェーホフの本領である。ペテロの悲しみが、おばあちゃんたちの間近に迫ったことを学生は信じることが出来た。そのときである。ゆらぐ物音が聞こえてきたのは。一方の端、チェーホフはそう記した。現在、他の端は限りなく遠い。
鶏が鳴く前に、ペテロは三たび裏切る。三度とは数限りなくということだと喝破したのは武田泰淳だった。裏切りはむしろ常態であることを知る人の、おそろしい発想である。チェーホフはそのことも踏まえ、もう一歩踏みこんだ。小さな声で。老いたものの無言の背姿が、途上にたたずむ若者に深い感動を与えることはよくある。『童年往事』の侯孝賢や『眠る男』の小栗康平など、映像で丹念に描いている。チェーホフは、老いたものが逆に学ばされる事態を描く。一方の端に触れたら、もう一方がゆらぐ、よもや、たまゆらのことではないであろう。もう一方とは他者性のことである。
感動におののく神学生の心境をチェーホフはこういう。【すると喜びが急に胸にこみあげてきたので、彼は息つくためにしばらく立ちどまったくらいだった。「過去は」と彼は考えた、「つぎからつぎへと流れだす事件のまぎれもない連鎖によって現在と結ばれている」と。】端がゆらぐとは、『眠る男』のなかで深く意識されていたイェーツの、自然の一部であるこころの営みは、互いに流入しあい、絶えず変化する出遭いを繰り返しながら小さな力を喚起する記憶力だという、おおいなる示現のことをいっているようにおもえてならない。
|