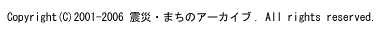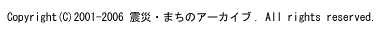木内寛子さんを想う時、ひとつの風景が立ち現れる。
静かな湖。さあっと風が吹くと、湖面に小波が立つ。やがて雲間から少しづつ日が射し始め、きらきらと光の乱反射。ほとりで眺めていると、いつしか心が慰められている。いつも静かで、優しい人だった。
そのほとりに立って、私は今悔いている。二年前の冬の入口、私たちは木内さんという、かけがえのない人を失った。それぞれが喪を過ごすなか、私は木内さんの書き残したものを読み返した。
療養中の便り、詩、日常感じたことを書き綴ったもの。一度は読んでいたはずなのに、読み込めていなかった。失って今、懸命に木内さんを求めている。生前に何故、この気持ちで木内さんと向き合わなかったかと、悔いている。
療養中の木内さんから、私たちに届く便りには、「家でできることがあればします」。と、必ずそうつけ加えられていた。辛い状況の中にいてなお、木内さんは「震災・まちのアーカイブ」という場とつながろうとしていた。その思いが、どこからくるのか、今になってわかり始めている。地震に遭って、木内さんはその日から被災者という、もう一人の自分を生きていくことになる。「この地震は、私にとって、渦の中にいた、はじめての体験だった。わたしは、と言うことの言いにくさ、違和としてありにくい空気を感じていた」。「いまも地震と関わっているのは、十把一絡げにされそうになった、されてしまった、あのころ報道などによって醸された勢いに対する、うらみ、であると思っている」。木内さんは、人間の傲慢や偽善を許さなかった。「いのち自体は地震の前に、どんな生きものも変わりないのだ」。その変わりないいのちを見つめながら、木内さんは抗い、傷んでいた。被災者と呼ばれて、押し込められていく力に。木内さんにとって、アーカイブとつながることは、その力への抵抗、そして、自分自信を生きる場を求めてのことだったのではないのだろうか。
木内さんが逝き、間もなく震災十年目を迎えた。「忘れない」。この言葉が、紙面やテレビの画面に溢れていた。あなたたちから言われたくない。木内さん、あなたがいたら、どんな思いでこの言葉を目にしていたことだろう。「忘れない」。いや、私はいつか木内さんのことを、忘れてしまうかもしれない。平穏な日を生きて。でもいつかある日、平穏が途切れる時、私は木内さんの見せてくれた湖のほとりに立つ。その時きっと、湖は現れる。木内さんの見せてくれた風景は私の中に残り続ける。それは、そう信じているのだ。
木内さんを送る。去り行く死者に別れを告げる。去り行く者に別れがたくついて行く。死者に別れを告げがたく、今もまだ、あなたのあとをついて行くように送っている。一年以上たった今もなお、私はそういう気持ちでいる。 |