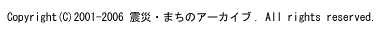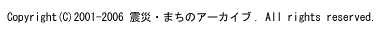建物が人をつくるとは、須賀敦子が女子大生のころ聴いたドイツの神父からの一撃だが、逆転したこの言いようはその後、私にも刻みこまれた。
【「つくる」という原罪】。宮本佳明は、新著の冒頭でこんな過激なことばを繰り出す。「建築の倫理」というタイトルのエピローグでは、【何か他のもののためではなく、ただ楽しいから、あるいはただ悲しいから歌う、そんな建築ができないものだろうか】註と、ポップスとしての建築を夢見る。【危うい生き物であること】を自覚する宮本さんは、存外手まり歌にうち興じる江戸の風変わりなお坊さんに近いのかもしれない。
事物はなぜつくられるのか。つくり、名づける行為が世界の始まりなら、原罪は超越者こそが背負うべきで、以後すべてはゆるされている。愉しいから、ただ哀しいから歌に委ねるとはそういうことだ。だがつくられて、在ること。それはいかなる事態か。宮本さんは建築家として逃れられない西欧的な構築性という考えを解きほぐそうと、手直し、再生という修復、補修の思想に注目する。以下、今年の夏のノートからのレポートである。
どこからともなく人が集まり、出遭い、眠るための容器(家)をつくる。眠る姿勢と、それを受け入れる地形との関係。この関係を問うことは都市論の初心だが、建築家は職能的に都市づくりに深く関わらざるを得ない存在である。宮本さんは記憶の器としての地形にこだわる。阪神大震災の二年後に書かれた冒頭論考「もうひとつの廃墟論」のなかの「地形的な癒し」は、何度読んでも感動的だ。
【仁川、夙川、芦屋川、住吉川、石屋川と、いくつもの天井川を越えて、西へ西へ理由もなく自転車のペダルをこいだ。そして、それが、肉体的な苦痛と同時に安らぎに似た感覚を与えてくれたことを覚えている。意味もなく、地形を歩くこと、自転車をこぐことで、震災を受け止めることができたように思えた。】
地形の解読方法が本書において示される。その一つが「環境ノイズエレメント」という考えである。ノイズとは、忘れられた掩体壕のような、風景のなかの異物のことである。宮本さんは土地の来歴を引き出しながら、都市を歴史の重ね書きとしてとらえる。
この考えを私は、ネクロポリス、証拠隠滅の水俣の埋立地を巡りながら抱いていた。眼前には、「二度とこの悲劇を繰り返しません」と刻印された慰霊碑。これでは広島の原爆慰霊碑と何ら変らぬものであり、どちらも加害の責任が明確な受難にもかかわらず、どうしてこうも主体の曖昧な発想に終止するのかと暗澹とした。足元の土の下には、漁師さんを苦しめた大量の有機水銀が不知火海の魚や貝や海老とともに埋まり、この場所に立つこと、歩くことは、亡くなったものらとのダイアローグに他ならなかった。
音楽家の港大尋さんの呼びかけで、水俣に来て今回で四度目。埋立地の水際で、宮本さんのことばを抱いたのは三度目だった。崩壊が人をつくる。壊れたからつくる、つくるから壊れる。建築の悲劇といわれるが、地震という崩壊の現場に立ち会った一人として私は、破壊から生まれる創造の欲望のなかに破壊が孕まれていることを身体で知った。そのことを一介の漁師である緒方正人が、違う方向から言い当てていることを知らされ驚嘆したことがある。
【潮の力とか海の力という圧倒的な力の前には、人間のつくったものなんてわずかな時間しか原型を保ちきらんという気がします。いずれ壊れる。おれはそのことに、どこかで心地よさみたいなものを感じますよ。】(『語り:つむぎだす』東京大学出版会)
正人さんには凄みがある。とりわけ防災(国防と読め)や歴史に携わる若い研究者は学ぶべきだ。支援者といっても、あくまで知識で関わる「よそもん」を一撃する迫力を読みとれないものが、お上の研究室に閉じこもった議論の明け暮れに自足できるのだろう。そこまでいえば脱線気味だが、研究者にありがちなやわな傾向は、石や草のことづてによって一度粉微塵になったほうがよい。いま踏みしめる地の草、足元に転がる石の存在に、畏れをもって近づき、遠ざかるべきである。
原罪なる発想から、癒しや和み好みの日本的思考はあまりにも遠い。だが原爆投下や水俣病のような理不尽な受難の場合、思考の様相は一変する。そういう場所では、ヤスパースの敗戦後の『戦争の罪を問う(責罪論)』などがいっきょに迫ってくるではないか。水俣の現地に身を置き、土地の風になぶられながらそうおもう。「チッソは私であった」という境地にたどり着き、今なお闘わざるを得ない漁師。高度経済成長の人柱である胎児性の患者さんを眼前にしたとき、よろぼう私を支えてくれたのが、【つくる人としての畏れ】を手放さない宮本佳明のエチカであったこと、夏の記憶として記しておこう。
註 1981年4月10日のシンポジウム「水俣が生みだす言葉、吉田喜重+原広司+土本典昭」で、建築家の原広司は、水俣の運動がもつメッセージはマイナスの中心としての「去りゆく空間」、何か哀しいとかいうのではなく、ものすごく晴れやかな感情移入を誘ってくれる喚起力ではないか、と発言していた。
|