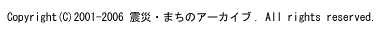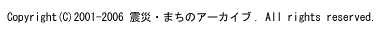|
|
|
|
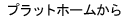  |
|
|
|
|
戦争と災害の土地をたどる
|
| 季村 敏夫 |
「ここにいるのが、信じられません」。地図を携えていても、なぜか歩行はそれてしまう。そのとき、この思いがうずく。一瞬に過ぎる跫音を追うが、いまだかつて美しい歴史の足跡などなかったという声に打ちのめされる。緑のそよぎは酷薄である。五月、マロニエの風に吹かれながら、ぼくはハンガリーの首都ブタペストの石畳をたどっていた。
「信じられません」、声を発したのはシモン・スレブニク。全編証言だけでユダヤ人絶滅政策を描く映画『ショアー』(クロード・ランズマン監督)に出てくる。日本では十年前、戦後五十年の節目の年、阪神大震災と地下鉄サリン事件のなかで初めて上映された。
 |
『ショアー』は、記憶の痕跡が何ひとつない空虚から始まる。スレブニクは、四十万人虐殺されたポーランドの絶滅収容所ヘウムノから、奇跡的に生還した二人のなかのひとり。場所の破壊、ナチスによる証拠隠滅工作により、今は一面の緑、すっかり変貌した収容所跡に、三十四年振りに訪れたとき、冒頭の感慨が白髪混じる中年の彼を襲った。
尼崎市のJR福知山線脱線事故の現場でも、このつぶやきが人びとを襲ったに違いない。突如視界に飛びこむ、風景の異常な歪み。与えられた現実に追いつくことができず、時間の裂け目にうずくまる。場所の変貌は、人びとから言葉を奪い、悲嘆の底へ突き落とす。
誰もが見えない地図を抱えている。場所と地名に係わりながら、人は生き、そして死ぬ。地図は空間を封じこめているが、地名の裏側には、濃密な時間があふれている。その地図が塗りかえられる、場所の記憶が奪われ、痕跡すら消失するとは、いかなる事態なのか。
災厄からの復興、生き残った人は死者の記憶を背負い懸命に立ち上がる。だが復興の内的な過程で、ともすれば記憶の地誌は改竄され、切り棄てられる部分さえ出てくる。出来事の記憶と記録に携わるなら、このことに自覚的に在らねばならないという視点で、この一月、ぼくら「震災・まちのアーカイブ」は、「阪神大震災・記憶の分有のためのミュージアム構想展」(主宰・寺田匡宏)に係わった。主婦と若い研究者の果敢な分有だった。そこで、非当事者の伝達性を巡って、記憶マップという方法が提示された。地図的思考の実践である。戦争と災害に見舞われた土地をたどることにより、場所が背負う重層的な記憶を読みこみつづけた。東京、沖縄、水俣、ベルリン、アウシュヴィッツ、ワルシャワを巡り、さらにぼくは、プラハ・ゲットー跡、ブタペストへと足をのばした。
ところが、どの場所に移動しても、ここにいるのが信じられない、この思いに襲われた。死者は、どこにひそんでいるのか。死者を忘失する以前に、たぶん死者の方が、生者を見限ったのだ。森のなかの絶滅収容所という構図に象徴されるように、中欧と呼ばれる、周縁部のクラクフ、ワルシャワ、プラハ、ブタペストは、郊外に広大な平原と森を持ち、その萌える緑の光線のため、惨劇の記憶などなかったかのような眩暈に襲われたものだ。
掲載する写真は、かつてブタペストで勃発した動乱の痕跡である。欧州は石の文化だから、記憶の痕跡は廃墟として立ちはだかるが、徐々に染み入るように朽ち果てる木端、木片の文化を背負うぼくらは、記憶の刻印という発想がいまだ飲み込めず、見出せず、しかも周辺のアジア諸国に認知されないまま、彷徨しているように思えてならなかった。
|
|
| 毎日新聞 2005年6月10日夕刊 掲載 |
|
|
|
|