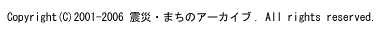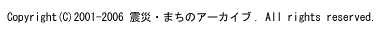なにごとも二度は起こらない
けっして だからこそ
人は生まれることにも上達せず
死ぬ経験を積むことも出来ない ヴィスワヴァ・シンボルスカ
起こりうることは既に一度起こったこと。つかの間に過ぎる人生の瞬間は永劫くり返される。これは超越者と対峙した西の国の思想だが、日本では、硬質で内在的な論理思考はとかく敬遠され、過ぎ去ればすべて美しき日々といった詠嘆に傾くことが多い。敗戦後の知識人を襲った戦争責任論のなかに、少数だが超越論的思考の提起があった。イエスの刑死に相当する思考方法を手に入れない限り、敗戦は経験とならないと受けとめられた。地震のあとも同様だったが、体験の教訓化という浅薄な啓蒙が際立ち、分野を横断する論議(経験を積むこと)はいまだに実現されていない。以下は、資料の保存活動の現場からの報告である。
一瞬に出現した瓦礫。失いたくない、死なしたくはない愛おしい物や人が焼け焦げる臭い。うち砕かれたそこに、裸の状態で投げ出される。これが本源的な姿であろう。今ここに在るアクチュアリティ。蹠に地面がある。見上げると空がある。いっせいに外のそよぎがおし寄せる。【なにごとも二度は起こらない】。一回限りに訪れる始原的なものから、一個の身体はついに逃れることはできない。外の現象に無関係ではありえないが、眼前の事実に指一本触れることができない。
挨拶から始まる。移動、侵入、横断。はじめに応答ありき、境界線を踏み越えて、呼びかけが響く。「ああ、何かせな」、後に「灘ボランティア」と呼ばれた人たちの呱々の声である。残された文字資料にはないが、映像に映る十一年前の彼らの口元から発せられている。私に出来ることはありませんか。声をかけさせてください。出来ることから始めようとおもいます。1995年1月17日。一人ひとりは内心の声に促され現地入りした。出遭いは偶然だが、一陣の風になること、先ず声をかけること。他者の苦痛へ近づき、そして遠ざかる。関わりつつ距離をもつこと、近さと遠さのあいだで揺れつづけながらの行為。世界への挨拶からすべては始まった。
居ないということ。いつもはそこで挨拶をかわせるのだが、忽然と消える。残された胸は、襲ってくる記憶に包まれる。記憶のなかの、おもかげ。小さな俤を抱く。あの日の不在への関与が、重くのしかかる。「人もろかりし/花もろかりし」、一瞬に消失したものからとり残される。不在に関わる体験。体験は、身体が裂かれつづける時間である。残された身体に記憶が疼く。そのとき俤の小ささが、いっそう哀切に吹雪いて来る。私たちがたまたま事務所で預かる震災一次資料。資料が収められたダンボ−ル箱を包む不可視の闇。そこに、生と死、集う息と消えた息、さまざまな面影が行きかう。
保存活動をすすめていると、資料の接し方をふくめ、その解読方法の根底的な変更を強いられることがある。読むことをいま一度読もうとする。きっかけはすべて、向こう側からやって来る。整理の現場にダイモンに似た声が現われ、おもわず手の動きが止まる。不在の出現である。昨年の暮れ、私たちは「灘ボランティア」と呼ばれた人たちと邂逅した。偶然性が出遭いを導いていた。そのとき彼らから、「なつかしい」という声が打ち上げ花火のようにあがった。すでに他者となった資料と、十年ぶりに再会した瞬間だった。
ノスタルジイは帰ることの苦痛、ギリシャ語のノストス(帰郷)とアルゴス(苦痛)の合成語である。本来は帰属できない距離の感覚を指すが、「なつかしい」という彼らには苦痛の翳りはまったくなかった。行為のあと、普通は取り返しのつかないおもいに苛まれる。やり直しがきかない。もう遅い。そんな声がたち現れる。過去が現在に浮かび上がり、未来が現在にひき寄せられ、異なった三つの時制がスパークする。ところが眼前の彼らは違っていた。ダンボールの箱から資料を取り出したときの声は予想外だった。活動継続中なら、歓声はあがらなかっただろう。意識は絶えず途上に在るので、いうまでもないことである。過去との対面。過去と現在の同時性。そのとき生じる痛みや疼き。過ぎ去った時間に関係の傷痕が息づくとき、感傷に浸ることは出来ない。歓声は、痛みとか疼きから奇跡的に遠い場所から放たれていたのである。
なぜ資料が今ここに在るのか。在ることへの驚き。資料とは、記憶とは、いったい何なのか。そのことを問うわれわれは、誰なのか。存在論であると同時に表象論、ボランティア論であると同時に時間論。地道な資料の整理解読作業は、予期しなかった場所に連れ出されていった。
|